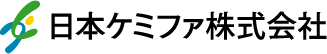新薬開発
当社は、まだ十分な治療薬がない病気に苦しむ患者さんのために、画期的新薬の開発を目指しています。長年にわたって培ってきたアルカリ化療法に関する技術や知見を活かした展開に加えて、ここ数年で大きく拡充・進展しているパイプラインのさらなる開発進展や裾野拡大を図り、各分野において最先端の研究を行っている企業・研究機関とのアライアンスにも積極的に取り組んでいます。
自社開発パイプライン
1. NC-2800 / オピオイドδ受容体作動薬(抗うつ・抗不安薬)
当社と筑波大学、北里大学、国立精神・神経医療研究センターの共同研究によって見出された、うつ・不安の治療薬として期待される化合物です。2015年にAMEDの産学連携医療イノベーション創出プログラム(ACT-M)に採択され、同機構の支援を受けながら、非臨床試験を実施しました。その結果、本薬剤の持つ治療薬候補としての可能性が高く評価され、2018年に同じくAMEDが行う事業である医療研究開発革新基盤創成事業(CiCLE)の支援テーマ※1として採択され、この支援を受けて2021年7月にフェーズⅠを開始しました。フェーズIは2023年度に終了しており、安全性に大きな問題はなく忍容性が確保されたことから、現在はフェーズⅡa実施に向けた準備を進めています。
また、2021年6月にはは住友ファーマ株式会社とNC-2800の共同研究開発契約、ならびにオプション契約を締結しており、同社がCiCLE事業の研究開発に分担機関として参画しています。
うつや不安などの気分障害は、年々患者数が増加している一方、医薬品による治療満足度は約4割にとどまっています。NC-2800は副作用の影響が少なく、安全性と有効性のバランスに優れたファースト・イン・クラスの薬剤となることを期待しています。
(※1 研究開発課題:オピオイドδ受容体活性化を機序とする画期的情動調節薬の開発、支援期間:2018年3月30日〜2028年3月31日)
2. NC-2600 / P2X4 受容体拮抗薬(神経障害性疼痛治療薬・慢性咳嗽治療薬)
当社は九州大学と共同で新規作用機序の神経障害性疼痛治療薬の研究を進めてきました。2012年度より国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)、2015年度からは課題を承継したAMEDの支援を受けて本テーマの開発を進め、2017年度にフェーズⅠを終了しています。
また、2020年度以降は本剤のメインターゲットに慢性咳嗽を加えました。本剤の価値を高めるため、さまざまな疾患を対象とした共同研究を進めながら、国内外企業へ幅広く導出活動を展開しています。
3. NC-2500 / XOR 阻害薬(痛風・高尿酸血症治療薬)
現在の尿酸降下療法では、治療開始後の急激な尿酸値低下による急性痛風発作の発現が留意すべき点として挙げられていますが、NC-2500 はフェーズⅠ試験において血中尿酸値を徐々に低下させるという特有の作用が確認され、この問題の改善につながる可能性が示唆されました。2023年2月には中国企業とライセンス契約を締結し、現在は同社により中国での開発が進められています。
また、本剤はアルツハイマー病などに代表される神経変性疾患への効果を示す基礎データが得られていることから、同疾患をターゲットとした展開についても検討を進めています。
4. NC-2700 / URAT1 阻害剤(痛風・高尿酸血症治療薬)
NC-2500 と異なり、腎臓で尿酸の再吸収を担うトランスポーター「URAT1」を阻害する作用機序により、尿酸の体外への排泄を促進します。NC-2700 は非臨床試験において、強力な尿酸排泄促進作用を示すとともに尿酸の尿中排泄に伴って懸念される腎障害や尿路結石症の抑制につながる酸性尿の改善効果も確認されました。現在、国内外の企業に向けた導出活動を行っています。
導入パイプライン
1. DFP-17729 / がん微小環境改善剤(膵臓がん)
2020年3月に創薬ベンチャーのDelta-Fly Pharma株式会社(以下、DFP 社)とライセンス契約を締結したDFP-17729 は、酸性に傾いてがん細胞が増殖しやすくなっている腫瘍周囲の環境をアルカリ化することにより、腫瘍周囲の微小環境を改善する作用を有しており、難治性がんの画期的治療効果が期待されています。
末期の膵臓がん患者を対象とした臨床開発が同社によって進められており、2022年度にはDFP-17729 と化学療法剤を併用し、化学療法剤のみ投与の場合と生存期間を比較するフェーズⅡが終了しました。2025年3月よりフェーズⅡおよびⅢ試験が開始され、症例登録が進行中です。
2. DFP-14323 / 抗がん剤候補化合物(非小細胞肺がん)
肺がんは、部位別罹患数で男女とも4番目に多く年間12万人が診断されており、また、部位別死亡数が最も多いがん種で、年間およそ7万6千人が亡くなられています※2。
2022年3月にDFP 社とライセンス契約を締結したDFP-14323は、この肺がんのうち、非小細胞肺がんの上皮成長因子受容体(以下、EGFR)遺伝子変異陽性をターゲットとしています。
過去の研究から、本剤ががん免疫担当細胞の表面に存在するアミノペプチダーゼN と結合することでがん患者の免疫応答を強め、標準的な抗がん剤の投与量を減らしたうえで、副作用を増強することなく効果を高めることが示唆されており、特に末期や高齢のがん患者の治療剤として期待されています。
非小細胞肺がんのうちEGFR 遺伝子変異陽性でステージⅢおよびⅣの患者さんを対象としたフェーズⅡが終了し、2022年6月に開催された米国臨床腫瘍学会で成績が発表され、あらためてその有用性が示されています。2024年2月よりフェーズⅢが開始され、症例登録が進行中です。
※2 出典:国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(厚生労働省人口動態統計および全国がん登録)
動物福祉に配慮した動物実験
当社では、すべての動物実験を、動物実験の科学的かつ倫理的基盤となる3R※3に十分に配慮して実施しています。このため、法令および厚生労働省より通知された「動物実験等の実施に関する基本指針」などに従って動物実験を行うための社内規程を定めるとともに、動物実験委員会を設置して動物実験計画の審査を行い、承認された実験のみを実施しています。また、定期的に自己点検・評価を行い、動物実験が常に適正に実施されていることを確認しています。さらに、動物実験に関する知識・技術を深め、動物福祉を踏まえた動物実験の精度を高めるための教育訓練を実施しています。令和4年6月に一般財団法人日本医薬情報センターより、「厚生労働省の所管する実施機関における動物実験等の実施に関する基本指針」に適合しているとの認証を受けました。
※3 3R:Reduction(使用動物数の削減)、Replacement(代替法の採用)、Refinement(動物の苦痛軽減)
日本ケミファの公的研究費の運用・管理体制
当社は、「研究機関における公的研究費の管理・監査ガイドライン(実施基準)」および「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」等に基づき、国や国立研究開発法人等から配分される公的研究費を使用する研究について、公的研究費の不正使用および研究不正の予防ならびに対応に関する規程を定めており、当該規程に則り、以下の体制において適正に運用・管理しています。
| 最高管理責任者 | 代表取締役社長 |
| 統括管理責任者 | 創薬研究所担当役員 |
| コンプライアンス推進責任者 | 公的研究費に関係する部門の責任者 |
通報について
公的研究費を使用する研究において、不正の疑いのある問い合わせや指摘がございましたら、以下の通報窓口へご連絡ください。
匿名での通報も受け付けておりますが、具体的な調査へのご協力のお願いや結果を報告させていただくことがありますので、できるだけ氏名や連絡先をお知らせいただきますようにお願いいたします。
なお、お知らせいただきました個人情報は、上記の目的以外に使用することはございません。
通報窓口
publicfund_research@chemiphar.co.jp
通報の対象
公的研究費の不正使用、研究における不正行為(捏造、改ざん、盗用など)
通報いただく内容
・研究不正の具体的内容
・研究不正の具体的内容を不正とする科学的な合理性のある理由